「管理職」という言葉は、さまざまな場面で使われます。どういう人が管理職か聞かれれば、「会社で昇進により役職が付き、部下を持てば管理職になる」といった認識が普通でしょう。しかし労務管理の分野では、「管理職」という表現には少し気をつける必要があります。
経営者の中には、「管理職には残業代を支払わなくていい」と思っている人がいます。このような誤った認識で社員の労務管理をして、もしも社員との間で労務トラブルが起きた際、会社が払わなくて良いと考えていた残業代を「未払い賃金」として裁判所から支払い命令がなされ、思わぬ経済的ダメージを負うリスクがあります。
また、会社員で昇進して管理職になった人の中には、「管理職とは何か、残業代も出ず無制限に働かされてしまうのではないか」と漠然と不安に思う人もいるでしょう。法律的な観点で、自分はどのような立場であるのか、またどのような保護を受ける存在なのかを知っておくことは、自分自身を守ることにもつながるといえます。
今回は、労務管理に焦点を当てて「管理職」とは何か解説していきます。
「管理職」って何?
「管理職」とは何を指すのでしょうか。一般的には、会社などの組織内で部長や課長といった役職に就き、一定の範囲で部下のマネジメントをする者を指すでしょう。一方、法律上の扱いを考えるときには「管理監督者」という言葉を使います。「管理職」と「管理監督者」は同じ意味なのでしょうか。
かつてマクドナルドで店長として働いていた男性が、過労死寸前の長時間労働を強いられ、残業代も支払われなかったとして、会社を訴えた裁判がありました。会社としては、店長は「管理職」であるから労働時間の制限もないし、残業代の支払いも不要と考えていたのです。
ところが判決では、この男性は労働基準法第41条の「監督若しくは管理の地位にある者」(以下、「管理監督者」と表記します)には当たらず、残業代を支払わないのは違法であるとして、2年分の未払い残業代約750万円の支払いを会社に命じました。
つまり、一般的に「管理職」は、会社内の役職者・部下を持つ者というように、かなり広い意味で使われる一方で、裁判などの争いになったときに「管理監督者」と認められるには、部長・課長・店長といった役職などの名称にかかわらず、地位、職務、権限、待遇などを細かく見られたうえで、個別に判断されることになります。
以上から、「管理職」と「管理監督者」は別物と考えるべきです。「管理職である」ということはその組織内の意味合いでしかないため、「管理職には残業代を支払わなくて良い」と勝手に解釈してよい話ではありません。上記マクドナルドの裁判と同じような争いが多く起こる中で、判例によって「管理監督者」になるかどうかの考え方(基準)が整理されてきました。この基準は後ほど述べます。
「管理監督者」は普通の労働者とどういう違いがあるの?
ここで、「管理監督者」は普通の労働者と何が違うのかみていきます。
労働基準法の条文を一つ引用します。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
労働基準法では、多くの規制を設けて労働者を保護しています。例えば「使用者は原則として、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。」などです。上記の法第41条では、それらの規制のうち労働時間の規制、休憩を与える義務、休日を与える義務、時間外労働に対し割増賃金を支払う義務、これらの規制・義務を「管理監督者」には適用しない、とされています。
「管理監督者」に対しては労働時間・割増賃金などの規制が無いので、冒頭で述べたような「管理職には残業代を支払わなくても良い」とか、「管理職には何時間働かせても良い」という誤解が生じるのでしょう。
ここで注意が必要なのは、「管理監督者」であっても、「労働者」であることに変わりはないということです。労働基準法の「労働者」として適用を受けて保護されるが、同時に「管理監督者」にたるために、労働時間、休憩および休日に関する規定が法第41条で適用除外されているにすぎません。したがって、例えば年次有給休暇は「管理監督者」であっても通常の労働者と同じく付与しなければなりません。
どういう人が「管理監督者」になるの?
では、どのような要件を満たせば「管理監督者」と認められるかみていきましょう。
厚生労働省によれば「管理監督者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいいます。「管理監督者」と認められるためには、次の4つの点に当てはまることが必要です。
- 重要な職務内容を有していること
- 重要な責任と権限を有していること
- 現実の勤務態様が、労働時間の規制になじまないこと
- その地位にふさわしい待遇がなされていること
以上の4つを細かくみていくと、まず厚生労働省の定義に「経営者と一体」という表現があったように、労働時間の枠を超えて活動せざるをえないような重要な職務内容を有していなければ「管理監督者」とはなりません。経営判断を伴うような職務を担っていることが必要です。
次に、経営者から重要な責任と権限が与えられていることが必要です。会社内で「管理職」の立場にあっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、いちいち上司の決裁を仰ぐ必要があるとか、上司の命令を伝達するに過ぎないような者は、「管理監督者」とはなりません。店舗の店長という立場であっても、従業員の採用や解雇の権限が無ければ、「管理監督者」と言えません。
さらに、経営者と一体であるということは、時を選ばず経営上の判断や対応が要請されます。このため、一般労働者のように労働時間の管理がされている場合も「管理監督者」とはなりません。例えば、営業中は常に店舗に常駐しなければならない、あるいはパート・アルバイトなどの人員が不足する場合に、それらの業務に従事しなければならないといった状態では、労働時間の裁量があるといえず、「管理監督者」と言えません。
最後に、その職務の重要性から、一般労働者と比較して、給与・賞与・その他について相応の待遇がなされていることが必要です。「役職手当が●●円以上付いていれば良い」というような画一的な基準はなく、その会社内の一般労働者との比較で判断されます。先に紹介したマクドナルドの判例は、店長の給与が、残業時間を考慮して時給換算すると下位の職位よりも低額であることが、管理監督者性を否定する根拠の一つとされていました。
このように、「管理監督者」を争う場合、個々の具体的な労働実態を細かく見ていき、それぞれの判断基準に照らし合わせることで総合的に判断されることになります。
まとめ
「管理監督者」は、経営者と一体の立場にあるため、労働時間などの一部規制がかかりません。
これは、それらの規制をしなくて良いくらいに使用者(経営者)に近い存在であるという意味合いであって、「管理職になったのだから残業代を支払わなくて良い」というようなネガティブな意味合いが先行するものではありません。経営者と一体であるといえるような重要な職務・責任・権限を有し、労働時間の裁量があり、さらには相応の待遇でなければ、「管理監督者」とはいえないでしょう。
ただし、今回解説した内容はあくまで経営者と労働者がトラブルになった場合に、どのような基準で裁判所が判断をするかというものであり、現実にはこの通りの取り扱いがされていないことも当然あります。
経営者の視点で考えれば、「管理職」とされている人を過度な労働時間働かせていないか、通常の社員と比べて十分な待遇であるか、この2点に最低限留意していただくことが、最悪トラブルに発展したときにダメージを軽減することになるでしょう。
逆に「管理職」たる労働者の視点で考えれば、マクドナルド裁判のように労働時間が過労死ラインに達している、また待遇も下位の職位の者より低い、このような状況は労働基準法に著しく反しています。そのような会社からは離れることも考えるべきですが、まずは労働基準監督署などに相談し、自身の立場を理解したら、場合によっては自身の権利を守るために戦うことも考えるべきでしょう。

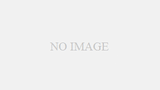
コメント